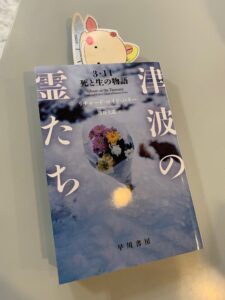
私は毎週月曜日の19時にテレビ東京で放送されている「YOUは何しに日本へ?」と「世界!ニッポン行きたい人応援団」という番組をよく観ています。
この番組の面白さは、文化の異なる外国人が、日本という国の文化に興味を持ち、日本の良さを訴えることによって、日本に住む日本人の私たちが、日本の社会、文化の良いところを再認識する、というところです。
日本の食文化、伝統文化、サブカルチャーだけで無く、日本人の立ち振る舞いや、礼節のあり方なども含め、日本という国が外国人から高く評価されることは日本人としてはとても気分がいいものです。
しかし、だからといって「日本最高!」と、有頂天になるのは軽率です。
番組は構成上、ネガティヴな意見を持つ外国人の発言は取り上げません。私としては、むしろ、テレビバラエティーでは決して取り上げられることのない外国人の率直な意見、日本人にとっては最早当たり前となってしまって気付き難くなってしまった日本の弱点を、外国人の目線を通して知りたいと思うのですが、テレビ番組の視聴者としては少数派かもしれませんね。
今回ご紹介する本は、日本在住のイギリス人ジャーナリスト リチャード・ロイド・パリー氏によって執筆された、学校の管理下では戦後最大と言われる大川小学校の惨事を記録したルポルタージュ『津波の霊たち〜3・11 死と生の物語〜』です。
日本人の誰もが知る3・11と大川小学校の事件が、外国人の目線にはどのように映ったのか、日本という国がどう映ったのか、それらの全てが、的確且つ克明に記された素晴らしい作品でした。日本の弱点も鋭く指摘されています。
内容紹介
在日20年の英国人ジャーナリストは、東北の地で何を見たのか? 2011年3月11日、東日本大震災発生。その直後から被災地に通い続けたロイド・パリー記者は、宮城県石巻市立大川小学校の事故の遺族たちと出会う。74人の児童と10人の教職員は、なぜ津波に呑まれたのか?
一方、被災地で相次ぐ「幽霊」の目撃談に興味を持った著者は、被災者のカウンセリングを続ける仏教僧に巡り会う。僧侶は、津波の死者に憑かれた人々の除霊を行なっていた。大川小の悲劇と霊たちの取材はいつしか重なり合い――。
傑作ルポ『黒い迷宮』の著者が6年の歳月をかけ、巨大災害が人々の心にもたらした見えざる余波に迫る。
日本人の習慣的弱点
大川小学校の事件は、ルールを守る事(決められた避難場所に避難する事)に固執したことによって起きてしまった惨事と言えます。
原則として、社会はルールを守る事によって秩序が保たれています。
震災時においても、被災者達の秩序を持った避難所での集団生活や、配給を待つ静かな行列は、海外のメディアでも繰り返し報道され、日本人の理性的な行動、受容の精神や我慢強さは、各国に広く評価されました。
しかし、著者はそんな日本人の持つ受容の精神や、過剰な我慢強さの正体は、人間や組織の失敗、臆病な心、油断、優柔不断を表すものであると指摘します。
日本という国を長い間抑圧してきた"静寂主義の崇拝"が、日本人の主体性をなくし大川小学校のような惨事を起こしたのではないかと。
日本人の宗教的弱点
作中にこんな文章があります。
" 事実として、仏教や神道などの組織的な宗教団体は、日本の個人的生活や国民としての生活にほとんど影響を与えていない。しかし何世紀にもわたって、仏教と神道は日本の"真の信仰"の儀式ー祖先崇拝ーのなかに組み込まれてきた。(p .175)”
世界的に最も信仰心の薄い国と言われる日本において、唯一の信仰として定着しているのが祖先崇拝であると、著者は指摘します。
つまり、特定の宗教を持たない日本人にとって、神とは、遠い祖先や、かつて家族であった故人という事になります。
確かにそうかもしれません。私自身、特定の神に祈る事よりも、仏壇や墓石にむかい故人に語り掛ける事がはるかに多く、違和感もありません。
ほとんどの日本人は、特別な教義や経典などは持たず、土地や家屋、故人、墓、遺骨、仏壇や位牌などを神仏の対象とし、それらに祈りを捧げることで心の平安を得てきたのです。
ところが、津波はそれらを全て奪い去ってしまいました。
信仰とは、神や仏を信じることで、その教えを拠り所にする事であると言われます。
津波は、日本人の信仰も、拠り所も奪い去ってしまったと言えるのではないか、と著者は訴えます。
信仰を失った人々は、人や物事を信用・信頼することが難しくなります。
それまで気にならなかった互いの価値観の相違は顕在化し、混乱や対立が生まれ、被災地での人間関係は徐々にばらばらとなって行きました。
大川小学校の遺族コミュニティも例外ではありませんでした。
日本人の鎮魂
震災は、日本人の精神性、宗教観だけでなく、政治、組織構造、人間関係の脆弱性を浮き彫りにしました。
そして著者は、混乱する被災地の取材の中で、相次ぐ心霊現象の話を耳にします。
亡くなった知人、日常的に死者と会話を始めるようになった人、「俺の中に何かいる」と訴え暴れる人、崩壊した住宅への出動を要請する通報を受けた消防士、倒壊した家屋に消えて行く男性を送り届けたタクシー運転手。
キリスト教、神道、仏教の宗教者のもとには、不幸な魂を鎮めてほしいという依頼がひっきりなしに舞い込んできました。
そんな中、著者は仏教僧であり祈祷師でもある金田住職に出会います。
被災者の救済を続ける日本人の金田住職の活動を通して、外国人である著者は真の救済とは何かを徐々に見出して行きます。
金田住職の示した、真の救済とは何か。
それは私が稚拙な文章で説明するよりも、是非この本を読んでご自身の目で確かめて頂きたいと思います。
とても素晴らしい事が書いてありました。決して読んで損はしないとお約束致します。
最後に
本書は、著者リチャード・ロイド・パリー氏によって書かれた英語の原作を、訳者 濱野大道氏によって翻訳されたものになります。
日本のことを一旦イギリス人が英語で説明し、その文章を日本人が日本人に向けて翻訳するという行程が、この本を読みやすく洗練されたものにしているような気がしました。
時系列で淡々と説明するのではなく、ミステリー小説のように、クライマックスへぐいぐいと引き込んで行く構成も良かったと思います。
震災から10年目を迎えた今年、あの日が私たち日本人にどのような影響を与えたのか、そしてどのような教訓を与えたのかを再び考えるとき、外国人の目を通して書かれた本作は、客観的でありながらも慈愛に満ちた素晴らしいメッセージに溢れていました。
困難の中でも懸命に生きる全ての人々に、この本をおすすめします。
