
2025年も残りあと二ヶ月となり、季節はぐっと秋めいてまいりました。スポーツの秋、食欲の秋、そして読書の秋ですね。今年話題になった本といえば、映画が大ヒットした吉田秀一の『国宝』をあげる人が多いとは思いますが、今回は私の本年度ベスト5をご紹介したいと思います。全て選りすぐりの傑作ばかりですので、面白い本を探している方は是非参考にして頂けたらと思います。
柚木 麻子『BUTTER』
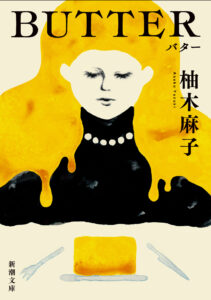
作品紹介
男たちの財産を奪い、殺害した容疑で逮捕された梶井真奈子(カジマナ)。若くも美しくもない彼女がなぜ──。週刊誌記者の町田里佳は親友の伶子の助言をもとに梶井の面会を取り付ける。フェミニストとマーガリンを嫌悪する梶井は、里佳に〈あること〉を命じる。その日以来、欲望に忠実な梶井の言動に触れるたび、里佳の内面も外見も変貌し、伶子や恋人の誠らの運命をも変えてゆく。各紙誌絶賛の社会派長編。
2007年から2009年にかけて複数の男性が一人の女性に次々と魅了され、搾取され、死に至り、逮捕収監後に取材に関わった週刊誌のデスクまでもが獄中婚に至ったあの"首都圏連続不審死事件"がの本作品のモチーフとなっています。
当時の報道や事件の概要を知っていれば、被害者の男性達はなぜあの女性に人生を奪われてしまったのかと疑問を感じ、自分なら絶対にあり得ない、被害者達はよほど迂闊な人間だったに違いない、といった確信を持ちながら本作を手に取るでしょう。しかし、容疑者"梶井真奈子(カジマナ)"の巧みな話術によって主導権を奪われ、日常を変えられて行く主人公"町田 里佳"同様、読者もまたカジマナに感化され、幾多の被害者と同じように自分も確実に誘導されていることに気付き思わず戦慄する、という驚愕の読書体験が本作の魅力の一つです。正直に打ち明けますが、私の実生活のバターの購買量、消費量は確実に増えました。本作の影響でバターの消費量が上がり、高騰し続けるバターの価格が更に高騰するような事がない事を祈ります。
王谷 晶『ババヤガの夜』

作品紹介
世界最高峰のミステリー文学賞
英国推理作家協会賞 ダガー賞 翻訳小説部門
受賞作
お嬢さん、十八かそこらで、なんでそんなに悲しく笑う――。暴力を唯一の趣味とする新道依子は、腕を買われ暴力団会長の一人娘を護衛することに。拳の咆哮轟くシスターハードボイルド!
『ジョン・ウィック』『イコライザー』『アトミック・ブロンド』のようなバイオレンスアクションの傑作に心躍らせてきた我々にとって、魅力ある新たな主人公の登場は最も歓迎すべきことです。『ババヤガの夜』に登場する新道依子もそんな我々の期待に応えつつ、これまで観たことのない新しい主人公像を見せてくれました。私が特に感じたのは、バイオレンスアクションというジャンルの持つジェンダーバイアス(「男らしさ」「女らしさ」といった性別による固定的な役割や行動への先入観や偏見)を逆手に取った手法です。性別による偏見に無自覚な読者であっても、作中のカタルシスこそが自身の持つジェンダーバイアスであり、その驚きや意外性が作品を極めて面白くしているという点です。私は「これは絶対映像化される!」「世界中で映像化権の争奪戦が起こるに違いない!」と思いながら読み進めていたのですが、ラストで明かされる衝撃の事実にこの作品の映像化の難易度が異常に高いことに気づきました。同時に活字によってしか表現できないこんなクライマックスがあったのかと感心させられたことは嬉しい誤算でもあります。私が思い付かないような何か素晴らしいアイデアで映像化はされるかも知れませんが、とりあえず現時点では書籍でしか味わえないハードボイルドバイオレンスアクションの傑作を是非!
窪田 新之助『対馬の海に沈む』
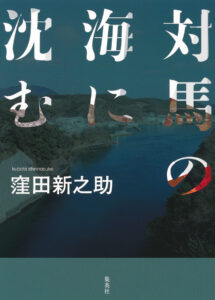
作品紹介
人口わずか3万人の長崎県の離島で、日本一の実績を誇り「JAの神様」と呼ばれた男が、自らが運転する車で海に転落し溺死した。44歳という若さだった。彼には巨額の横領の疑いがあったが、果たしてこれは彼一人の悪事だったのか………? 職員の不可解な死をきっかけに、営業ノルマというJAの構造上の問題と、「金」をめぐる人間模様をえぐりだした、衝撃のノンフィクション。
閉鎖的な空間が舞台の群像劇というフォーマットは、社会や人間という複雑で多様なものを"縮図"として具体的に浮かび上がらせることが出来るため古来から様々な作品に用いられてきました。その普遍的なフォーマットが現実の事件と重なるとき、登場人物の歪さや結末の儚さは寧ろ圧倒的なリアリティとなり、想像を超えた極上のエンターテイメントに昇華するのだという事を強く感じた読書体験でした。対馬という閉鎖的な場所で起きた群像劇は、俯瞰すれば全国で、さらには世界中で起きてきた、あるいは起きているであろうことは容易に想像できることであり、規模感の違いこそあれ全ての生活に密接であると思えてなりません。
『対馬の海に沈む』読了後、興奮冷めやらぬ私は、これまで全く馴染みの無かった長崎県対馬市の地図を開き、本編登場する地名や施設を探してみました。100を超える小さな離島で形成されたその複雑過ぎる地形は、美しい自然にも、過酷な環境にも、事件に関わる様々な人間の心理のようにも見えました。
村田 沙耶香『世界99』

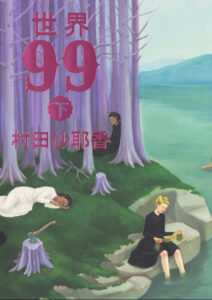
作品紹介
性格のない人間・如月空子。彼女の特技は、“呼応”と“トレース”を駆使し、コミュニティごとにふさわしい人格を作りあげること。「安全」と「楽ちん」たけを指標にキャラクターを使い分け、日々を生き延びてきた。空子の生きる世界には、ピョコルンがいる。ふわふわの白い毛、つぶらな黒い目、甘い鳴き声、どこをとってもかわいい生き物。当初はペットに過ぎない存在だったが、やがて技術が進み、ピョコルンがとある能力を備えたことで、世界は様相を変え始める―。性格のない「からっぽ」の空子の一生と人間社会の終着点を描いた、全世界注目のディストピア大長編!
「読んでよかった!」と「読むんじゃなかった…。」が混在する小説にハズレはない!が持論の私にとって、その言葉通りの小説が『世界99』です。
私は小説を読んでいる時に声が出ることはほとんど無いのですが、『世界99』〈上〉終盤と、『世界99』〈下〉終盤の合計2回、「読んでよかった!」と「読むんじゃなかった…。」が混ざり合った正真正銘の呻き声が出ました。間違い無く奇矯な小説と言えますが、奇矯なだけではなく設定も、人間描写も鋭く、説得力に溢れ、ディストピア小説の古典的名作『1984年』の最新アップデート版として読む事もできると思いました。特にピョコルンにピョコルンというサンリオキャラクターのような名前を付けてしまう作者の悪意とセンスは"最悪で最高"としか言いようがありません。
万人におすすめと言い切れないところが残念ですが、最悪で最高を求める猛者のあなたであれば『世界99』はベストな選択です。
岸田 奈美『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』

作品紹介
笑えて泣ける岸田家の日々のこと
車いすユーザーの母、
ダウン症で知的障害のある弟、
ベンチャー起業家で急逝した父――
文筆家・岸田奈美がつづる、
「楽しい」や「悲しい」など一言では
説明ができない情報過多な日々の出来事。
笑えて泣けて、考えさせられて、
心がじんわりあたたかくなる自伝的エッセイです。
今年一番読んだのは岸田奈美作品でした。出版されている書籍だけでなく、noteやYouTube、ネット上の様々なコンテンツも追いかけていました。
私自身、日頃から悲しみや困難をユーモアに変換する技の鍛錬に勤しんでいるつもりですが、岸田奈美という達人を目の当たりにし、その洗練された技の素晴らしさに平伏しているような状態です。多分、私が書きたいと思っていることのほとんどを、私の何十倍ものクオリティで書いているのが岸田奈美作品だと思って下さい。
作品紹介に"笑えて泣けて"とありますが、私は泣きながら笑っている人を見ると、急に涙が出そうになります。きっとその泣きながら笑っている人の言葉に出来ない感情や、不器用な優しさに深く共感し、同じ思いをした同類として親近感を感じているからなのだと思います。涙が出るようなことは消耗するのでできれば頻繁にあって欲しくはないですが、そんな涙を感じる度に、世界がなかなか捨てたものでは無いと感じる訳ですから、泣きながら笑っている人、悲しみや困難をユーモアに変換している人には積極的に、恒常的に関わるべきだと私は考えています。なので、岸田奈美なのです。とにかく今ここでこの文章を読んで下さっている方々に私は言いたい。私の文章なんかよりまず『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』を読んで下さい!そしてその流れで他の関連作品も読んじゃって下さい!そこには泣きながら笑う人も、悲しみや困難をユーモアに変換する奥義も、全てが詰まっています。達人の教えの元、互いに技の鍛錬に勤しみましょう。ありがとうございましたっ!
以上、2025年 私が読んでよかったと思った本を5つ紹介させて頂きました。あなたの読んでよかった本も是非教えて下さいね。ではまた。
